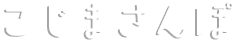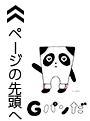畳縁の歴史は、畳の歴史とほぼ同じであるとされている。現在のような厚みのあるものに進展する前に、表に端(へり)をつけたものを畳とする段階が奈良時代にあり、のちに畳床が加わって今の形になった。いくつかの文献には畳の発祥・生成と同時に畳の端に細幅の織布または皮を縫い付けたことが記されている。
畳縁の歴史は、畳の歴史とほぼ同じであるとされている。現在のような厚みのあるものに進展する前に、表に端(へり)をつけたものを畳とする段階が奈良時代にあり、のちに畳床が加わって今の形になった。いくつかの文献には畳の発祥・生成と同時に畳の端に細幅の織布または皮を縫い付けたことが記されている。
 隋書倭国伝では「草を編みて薦となす。雑変を表となし、縁るに文皮をもってす。」とあり、また東大寺献物帳では「黒地の錦端畳」と記録されており、奈良時代にはすでに手近かにある資材を応用するという多様化段階にあったことを示しているようだ。
隋書倭国伝では「草を編みて薦となす。雑変を表となし、縁るに文皮をもってす。」とあり、また東大寺献物帳では「黒地の錦端畳」と記録されており、奈良時代にはすでに手近かにある資材を応用するという多様化段階にあったことを示しているようだ。
その証として正倉院に保存されている聖武天皇(730年代)の御床は「床に真菰のむしろ6枚を重ね、ところどころ麻糸で綴じ、その表にいむしろ、裏に麻布をとりつけ花文錦の縁を取ったもの」との記録がある。
畳表の切り落としである巾部分を保護補強するための布製の素材で、この畳縁をしっかり縫うことで型崩れ・ほつれが無くなるというわけ。まさに畳の要の部分。
畳縁はその実用性と装飾性の上から当時すでに不可欠の存在になっていたのだ。
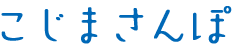

 Select Language
Select Language